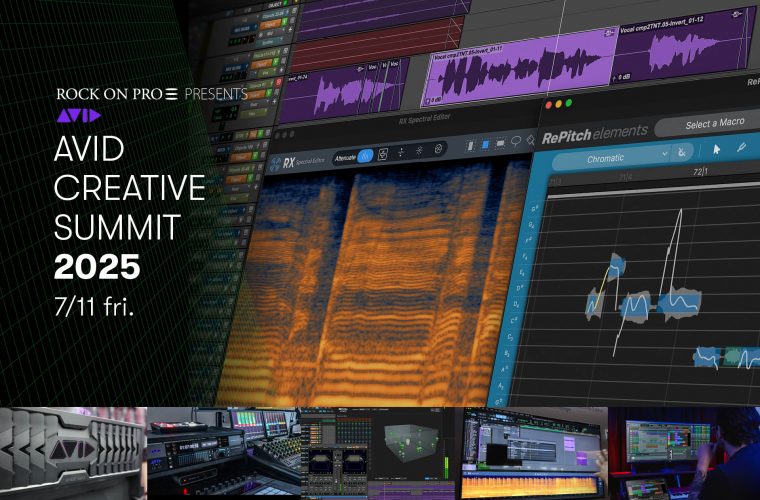Ozone 9~10で追加された機能【ミックスマスタリング学園】

OzoneといえばMaster Assistantと言っても過言ではない程度にはOzoneの目玉機能であるMaster AssistantはOzone 8で初めて追加されました。AIが楽曲を聴いて、マスタリングの最適なスタート地点を提案してくれる機能で、マスタリングに不慣れな人やマスタリングにあまり時間と手間をかけたくない人の救世主として広く受け入れられました。
その後もバージョンを経る度に改良が加えられ、現在のOzone 11ではジャンルごとに最適なマスタリングのスタート地点を提案してくれたり、ボーカルの音量バランスが適切か見直してくれたり、ラウドネスの値を保ったままよりクリアに聞かせてくれたりと、大きな進化を遂げています。
ただ、こうしたナンバリング系のツールは今自分がどのバージョンを持っているかも忘れがちですし、知らない間に自分が持っているバージョンよりも2~3世代先のものがリリースされていて、アップデートすることで何が新しくなったのかが分からないなんてこともよくあることだと思います。
Ozone 11の新機能は製品ページを見れば出てくるので、本記事では敢えてOzone 9やOzone 10で追加された当時の新機能を振り返ってみることで、旧バージョンのユーザーの方が最新版にアップデートすることで得られる恩恵をお伝えしていきます。
Ozone 9で入った新機能は大きいところだと下記の4点です。
- Master Rebalanceモジュール
- Low End Focusモジュール
- Match EQモジュール
- Imagerの新モード
Master Rebalanceモジュールでは、ミックス済の音源からベース、ドラム、またはボーカルのみを分離させリアルタイムに音量を変更することができます。リアルタイムということは、オートメーションを書くこともできるということです。これにより、例えばマスタリングの際にサビの入口だけボーカルを少し強調したい、といった調整を細かいEQの設定などで行うのではなくダイレクトにボーカルの音量に対して行うことができます。
Low End Focusは読んで字の如く、ローエンドのフォーカスを合わせたりぼかしたりすることができます。画像編集ソフトでコントラストを上げるようなイメージで、ローエンドのエネルギーの大きい部分と小さい部分の差を広げたり狭めたりすることができます。これによって、EQやコンプレッサーなどの古典的なツールでは難しかったローエンドの処理が簡単に行えます。
Match EQでは2つの波形の周波数特性を簡単にマッチングすることができます。自分が好きな曲のマスターのトーンに近づけるような使い方もできますが、トラックに使っても非常に便利です。例えばギターやボーカルをマイクでレコーディングしていて途中で休憩のためにマイクの前から離れた場合、録音を再開した時に微妙にマイキングが変わってしまって音色が上手く繋がらないといったことが起きます。そんな時に休憩前のテイクと後のテイクをMatch EQで合わせれば、全てを録り直したり、マニュアルのEQ操作でトーンを合わせる労力をかけることなく手軽にトーンを揃えることができます。
Imagerにはモノのソースをステレオに広げる2つめのモードが追加されました。こちらの方が高い数値に設定してもトランジェントをより保持してくれます。
Ozone 9でもMaster Assistantが改修されましたが、後のバージョンで更に大きな変更が加わっているためここでは割愛します。
さてOzone 10ではどのようなアップデートがあったでしょうか。主なポイントは以下の4つです。Master Assistantの改良もありましたがOzone 9と同様にここでは割愛します。
- Impactモジュール
- Stabilizerモジュール
- MaximizerのSoft Clip
- Imagerのサイドの情報の復元
- Gain Matchの仕様の変更
Impactモジュールは波形の中の瞬間的かつ大きな音量の変化を4つの帯域に分けて操作するモジュールです。難しく言いましたが、要するに4バンドに分割して音のインパクトを強めたり弱めたりするモジュールです。これにより、マスターの中のキックやスネアのインパクトの強さをコンプレッサーに頼らずに調整できるようになりました。
StabilizerモジュールはOzoneの中にあるジャンルごとの理想のトーンカーブと現状の信号を比較し、その差を埋め続けることができるモジュールです。Stabilizerは直訳すると「安定させるもの」ですが、「このジャンルの音楽だったらこういうトーンがいいよね」というゴールに向けて波形のトーンを安定させ続けてくれます。ジャンルターゲットは自分で選んでもいいですが、Master Assistantを使えばStabilizerにジャンルターゲットが設定された状態になるためまずはMaster Assistantにまかせても良いでしょう。
MaximizerにSoft Clipが追加されたことで、音が割れたり潰れたりすることを防ぎながら聴感上の音量をより高められるようになりました。
Imagerでステレオ幅を狭めた場合両サイドにあった成分の存在感が希薄なってしまう問題がRecover Sidesという新しいパラメータで改善されました。
Ozoneには処理の前後を同じ音量に揃えることで音量変化に騙されずに処理内容の是非を確認できるGain Matchという機能がありましたが、Ozone 10で仕様が見直され、処理を行う前の信号の音量を変えて処理後の信号の音量に合わせるようになりました。これにより最終的なレベルにおいてマスタリング前の波形がどんな音だったかを確認できるようになり、よりストレスの無いビフォーアフターの比較ができるようになりました。
これらがOzone 9と10で追加、改良された主な機能です。Ozone 11の新機能と併せてこれらを改めてご確認頂くことで、最新バージョンを使うことのメリットがクリアになれば幸いです。